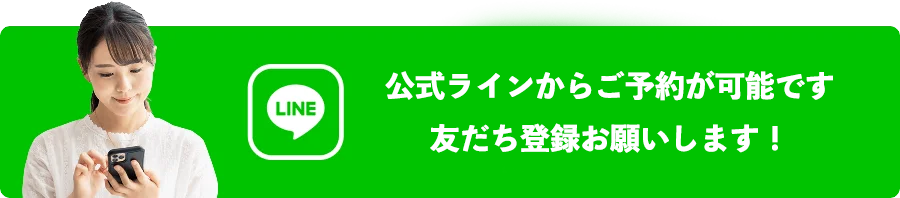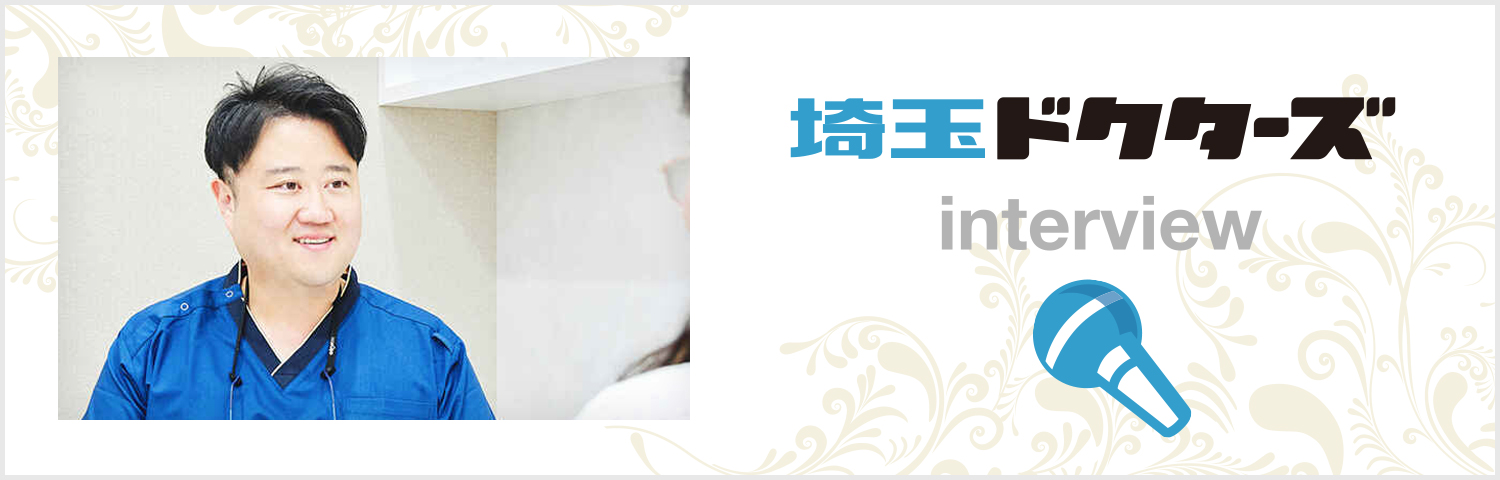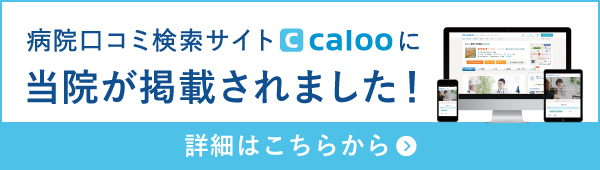小児歯科
目次
親子で安心して通える
歯科医院へ

埼玉県さいたま市・与野駅前の歯医者・歯科医院【与野さとむら歯科】は、ファミリー世帯の患者さまにも気軽にお立ち寄りいただき、リラックスして診療を受けてもらえる歯医者さんをめざしております。
小児歯科の経験豊富な女性の歯科医師、院長先生、矯正認定医とも連携し、虫歯の治療から予防はもちろん、お子さまの歯並びの矯正やポカン口の改善など幅広い症状に対応することができます。
お子さまの歯科治療とともに、保護者さまご自身の治療も安心して受けていただけるよう環境を整えておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
当院のやさしい設備
・小児歯科の特徴を
ご紹介

無料駐車場・駐輪場を併設
同じ建物にはスーパー(TAIRAYA与野店)をはじめとした商業施設があり、100台以上の駐車場と駐輪スペースをご利用いただけます。
また、当院の同じフロアには小児科クリニックもございますので、ご来院の際には一度の駐車で完結できますよ。
バリアフリーへの配慮
ベビーカーや車椅子のまま乗り入れしやすいようにと、バリアフリーにも配慮した院内設計となっております。
赤ちゃんや小さなお子さまをお連れの方も気軽にご来院いただけます。
キッズスペースや
キッズユニットなどもご用意
お子さまと一緒に楽しく通院できる環境づくりに取り組んでいます。
「子どもが泣いて周りに迷惑じゃないかな」と心配されている方も、安心してご来院ください。
『シャボン玉石けん』
特約店の歯医者さん

無添加・オーガニック商品を
院内でも採用しています
世代をこえて “未来の健康を守る” 歯科医院をめざしている当院は、自然派思考のみなさまにも安心してご来院いただきたいと考え、また病院から排出されるものも自然にやさしいものでありたいから——。
無添加・天然由来の成分にこだわった『シャボン玉石けん』を院内でも採用し、お口のケア用品やハンドソープなどオーガニック商品を院内の売店でも取り扱っています。
『よのさとKIDS
クラブ』も好評です

地域のお子さまの未来の健康と
笑顔をつくるお手伝い
「歯医者さんに楽しくきてもらい、小さなころから自分の歯を守る正しい知識と習慣を身につけて欲しい!」という願いから、『よのさとKIDSクラブ』を開設しました。
よのさとKIDSクラブとは?
毎月1回、お子さまの年齢やお口に合わせた歯磨き指導や、歯並びに関係している舌・唇・頬などの筋肉を鍛えるトレーニング、お口の健康を守る勉強会などを開催。
2025年11月よりスタートし、現在もたくさんのお子さま・親御さんにご好評をいただいております。
対象
0歳〜15歳
入会費
3,300円(オリジナルトートバック、ファイル、歯ブラシのセットをプレゼント)
※詳しくはお気軽に当院へお問い合わせください。
当院の小児歯科の
診療方針について

お子さまの将来の健康を
見据えた優しい診療を
幼いうちに歯科に対する苦手意識が芽生えてしまうと、大人になってからも歯医者に通いづらくなり、結果として将来的に歯の健康を損なう原因となってしまう場合があります。
実のところ、院長先生自身も子どもの頃は歯医者さんが苦手で虫歯が多かった経験もあり、地域のお子さんには同じような思いはしてほしくないと考えています。
そのため当院では、ご来院時にお子さまの歯に緊急性の高い症状がない場合には、無理に治療を進めるのではなく、少しずつ歯医者さんの雰囲気に慣れてもらうところから始めます。
お子さまの気持ちに寄り添いながら、歯医者嫌いにならないようにステップを踏んで進めていく診療を大事にしています。
子どもの虫歯と
予防ケアについて

大切なお子さまの歯と
健康を守るために
「どうせ乳歯は生え変わるのだから…」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、虫歯にならないためのメインテナンスを欠かさないことや、虫歯になってしまった場合の治療が大切なことは、子どもでも変わりません。
むしろ子どもの方がその重要性は高いと言えます。
小さな頃から正しい知識と生活習慣を身につければ、大人になってからも歯の健康を保てる可能性が大きくなります。
当院は乳幼児から小学生を対象に、闇雲に歯を削ったり抜いたりしない、健康的な成長を助けるためのケアを行います。
子どもの歯は虫歯になりやすい?
大人の歯と比べると、子どもの歯は虫歯になりやすい状態にあります。
同じ永久歯であっても、子どもの歯はまだ再石灰力が弱く、エナメル質や象牙質も薄いからです。
特に乳歯が虫歯になった場合、痛みを感じにくく進行も早いため、虫歯がかなり進行した状態で発見されることが少なくありません。
乳歯の状態は、生えかわる将来的な永久歯の歯並びなどにも影響を与えますので、お子さまの大切な歯の健康を守っていくために注意が必要です。
虫歯リスクを高めてしまう
原因について
“毎日歯磨きをしているはずなのに、虫歯を繰り返してしまう…”という方は、歯磨きの仕方以外にも虫歯リスクを高めてしまっている原因があるかもしれません。
虫歯リスクに関わるポイント
歯並びの不正
歯並びが整っていないと歯を磨く際にうまく歯ブラシが届かない場合があります。
汚れが溜まりやすくなってしまうことで、結果として虫歯リスクに影響します。

歯の形態
歯の形や大きさは人によって異なります。
歯の表面の溝がプラーク(歯垢)の溜まりやすい形状である場合など、虫歯リスクが高まります。

噛み合わせ
就寝中の歯ぎしりや、特定の歯に負担がかかる噛み合わせである場合も虫歯リスクを高めてしまいます。

唾液の分泌量
口の中が乾燥した状態が続くと、お口の中の細菌が増殖しやすい状態となります。
いつも口呼吸をしている場合など、虫歯リスクは高まります。

食生活
砂糖を多く含むものや、歯に付着しやすい食べ物を頻繁に摂ったり時間をかけて摂取することで虫歯リスクを高めてしまいます。

生活習慣
不規則な食事、就寝前の飲食など、そうした習慣は歯の表面の再石灰化を阻害し虫歯リスクを高めてしまうことにつながります。

お子さまの一生の歯を守る習慣
お口の状態や年齢によっても適切な口腔ケアは異なり、また、お子さまのお口の中の小さな変化や症状の予兆を見逃さないためにも、定期的に歯科医院で検診を受ける習慣を身につけて、早期発見・早期治療につなげていくことが大切です。
定期的な歯科検診に通うことで、虫歯やお口のトラブルを初期の段階で発見することができれば、治療時間や費用も少なく済み、お子さまへの負担も軽減することができます。
また、お口の状態に合わせて、フッ素塗布やシーラントなどの予防ケアを取り入れていくことで、お子さまの歯の健康を維持しやすくなります。
歯医者さんでの
診療方針について
虫歯予防ケアメニュー

フッ素塗布
歯の表面にフッ素を塗布することで、歯質を硬くし、歯の再石灰化を促します。
特に歯質の柔らかい生えたての乳歯や、乳歯から永久歯へと生えかわったばかりの時期に行うと効果的です。
また、初期虫歯であれば、再石灰化によって治る可能性もあります。
フッ素塗布を定期的に行うことで、虫歯になりにくい環境を作り上げていきます。
シーラント
虫歯になりやすい奥歯の溝を、フッ素を放出する薬剤(シーラント)で埋めることで虫歯になりにくくする予防ケアです。
歯を一切削る必要がなく、痛みもありません。
奥歯の溝にできる虫歯は、生え始めから2~3年以内にできやすく、特に溝が深く複雑な6歳臼歯に効果的とされています。
歯磨き(ブラッシング)指導
お子さまのお口周りも日々成長と変化を続けています。
その変化に伴い、口腔ケアの仕方や注意しなければならないことも変わるため、当院では、その時にベストな指導やアドバイスを行なっています。
効果的な歯磨きの仕方を身につけ、ご自宅でも継続していくことで予防への意識を高め、お子さまの将来の健康へとつないでいきましょう。
子どもの歯並びが
気になる方へ

理想の歯並びを得るための
小児矯正治療
歯並びや噛み合わせに問題がある場合は、矯正治療のご提案もしています。
永久歯に生え変わる12歳頃までの間は顎の骨もまだ成長過程にあり柔軟性もあるため、矯正に適した時期といえます。
もちろん一生の歯並びや噛み合わせを左右する大切な矯正となりますので、事前にカウンセリングをしっかりとさせていただき、ご納得の行く選択をしていただけるよう丁寧にサポートいたします。