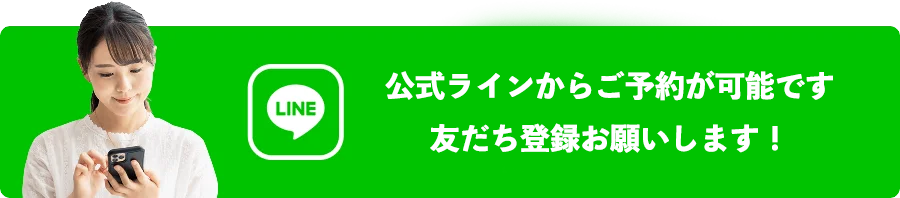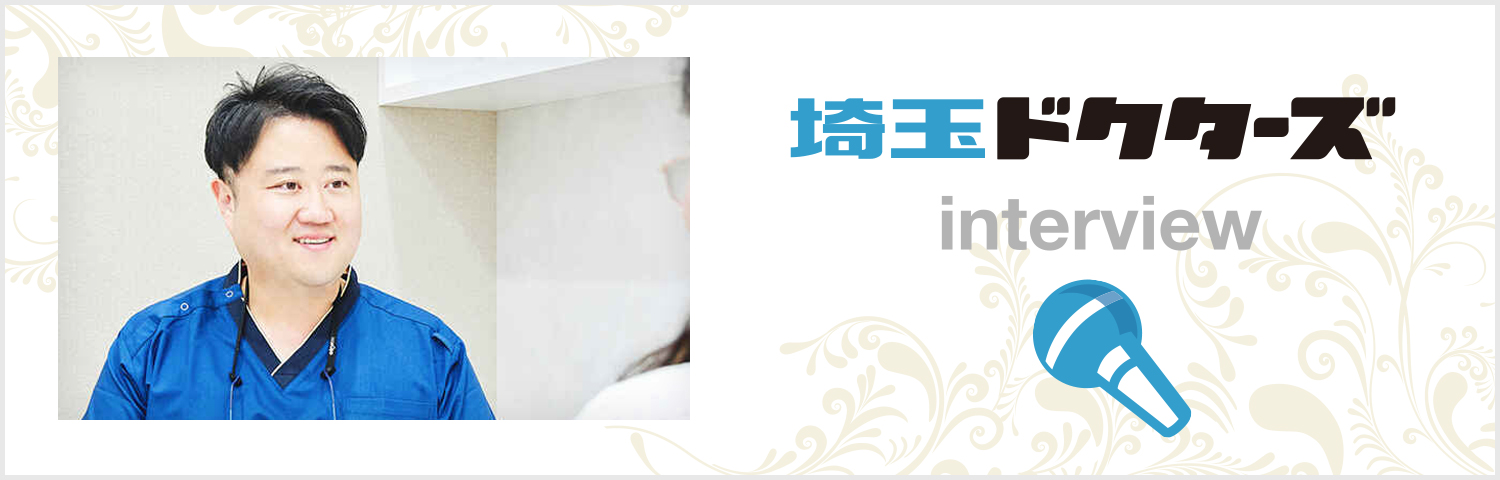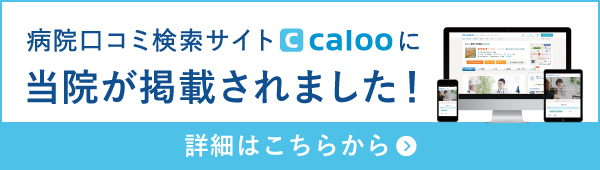小児矯正
目次
当院の小児矯正の特徴
について

当院の小児矯正の特徴
当院では、 機能的マウスピース矯正(プレオルソ)を導入しております。
お子さんの体の成長に寄り添いながら、 適切なアプローチをお父さんお母さんと一緒に考えます。
プレオルソを行うことで
- お口の周りの筋肉の機能を高め、
口元のバランスを整える。 - 正常な歯列へ拡大する。
- 舌が正常な位置を保つように誘導する。
上記の事が可能になります。

子供の癖が歯並びに
及ぼす影響

指しゃぶり
長い期間指しゃぶりを続けると、 前歯が前に出たり、 上下の前歯が噛み合わなくなったりすることがあります。
これにより 「出っ歯」 や 「開咬(上下の歯にすき間ができる噛み合わせ)」 の原因になることがあります。
口呼吸
口で呼吸する習慣が続くと、 口唇や舌の筋肉のバランスが崩れ、 前歯が出てきたり、 顎の骨の成長に影響が出たりすることがあります。 また、 口の中が乾燥しやすくなり、 虫歯や歯周病のリスクも高まります。
歯ぎしり
睡眠中の歯ぎしりは成長期には一時的なことも多いですが、 強い力がかかり続けると歯がすり減ったり、 顎の関節や歯並びに負担がかかる場合があります。 日中の歯ぎしりや食いしばりは、 ストレスや集中時の癖として表れることもあります。
頬杖
頬伺をよくする子供は、 顎の骨に片側から強い力がかかり続けることで、 顎の歪みや噛み合わせのズレにつながることがあります。 成長期の骨は柔らかいため、 特に注意が必要です。
子供の成長に合わせた
矯正開始のタイミング
について

子供矯正は
いつ頃始めるのがベストか?
小学校入学前後から始める子が多いですが、 実際それがベストかと思います。
遅くとも10歳くらいまでには始めたいです。
子供の矯正治療は
なぜ重要なのかについて

子供の矯正治療はなぜ重要ですか?
(歯並びが悪いことが
及ぼす影響など)
子供の矯正治療は、単に見た目の美しさだけでなく、将来の健康や生活の質に大きな影響を与える重要な治療です。歯並びやかみ合わせが悪いことは、さまざまな身体的・精神的な問題を引き起こす可能性があり、早期の矯正治療はその改善に役立ちます。
メリット
しっかり毎日プレオルソを使ってくれている子供達は比較的早期に結果が出てくる事が多いです。 その結果、 Ⅱ期治療 (大人になってからのワイヤーを使用した矯正など)をしなくて済むこともあります。
デメリット
大人になってから(中学生以降)の矯正治療は長期間の治療が必要になったり、 抜歯や顎の手術が必要になることもあります。
平均的な治療期間はどの程度か?
一つの装置で1年が目安ですが、 早期に結果が出てくるケースもあります。
時間がかからないケース
プレオルソを小学校入学前後から始めて、 毎日装置を使用してくれていると時間がかからない事が多いです。
時間がかかるケース
顎の位置や歯の位置が正常よりも大きくずれている場合はプレオルソでの治療が難しいです。
1期矯正について

使用する装置について
プレオルソという一体型マウスピース矯正装置を使います。
治療の流れについて
カウンセリング
お子様の現在の歯並びの状況、 生活習慣などをお聞きします。
大まかな治療期間、 費用なども説明します。

検査
口腔内診査、 レントゲン撮影、 お顔やお口の中の写真撮影などを行います。
場合によっては口腔内スキャナーを用いて3D模型を作成します。

診断
プレオルソを用いての治療が可能かをまず診断します。 可能であれば、 適切な装置の選定を行います。

治療開始
実際に毎日プレオルソを使用して頂きます。 夜と日中1~2時間の使用をお願いしています。
難しい場合は口に装置を入れて慣れる事から始めましょう。 1ヶ月に1回来院してください。

保定
目標の歯並びになってきた場合でも、 1年間はプレオルソを引き続き使用をしてもらう事が望ましいです。

メインテナンス
発音やお口の周りの筋肉が正しく使えるように、 あいうべ体操やポッピングなど簡単なMFTを続けるようにしましょう。

治療期間について
一つの装置で1年間が目安ですが、 途中で次の装置に移行したり、 その後のⅡ期治療に移行することもありますので、 患者さんによりケースバイケースになります。