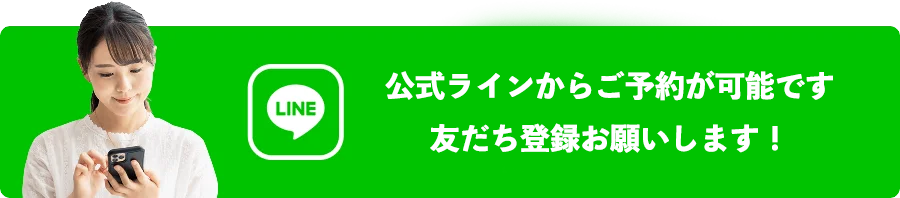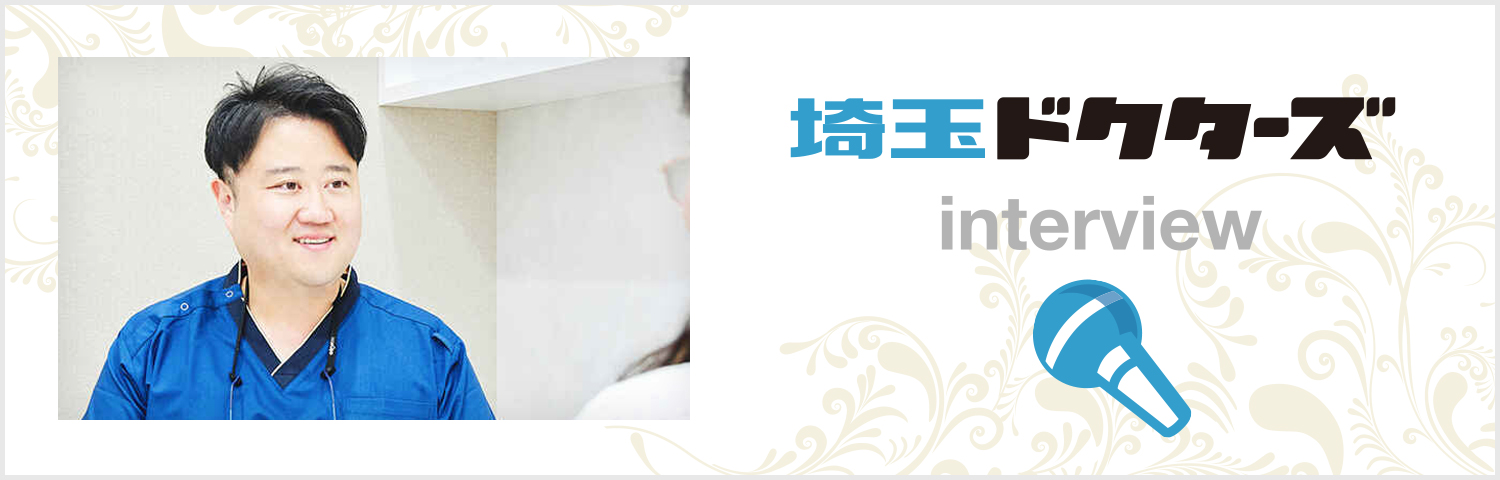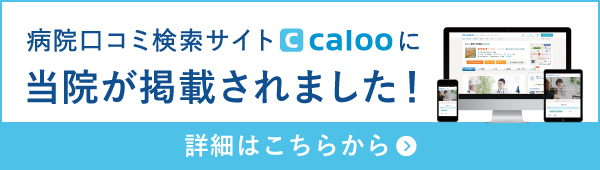歯周病
目次
埼玉・与野で歯周病の
専門的な治療が
受けられる歯科医院

このようなお悩みはありませんか?
- 歯周病(歯槽膿漏)が気になる
- 歯ぐきから血や膿が出る
- 他院で治療を受けているが、改善せず不安
- 他院で「抜歯」と診断されたが、抜かずに残したい
- 歯周病を根本から治療・予防したい
- 将来も自分の歯で食事を楽しみたい など
歯周病は生活習慣病であり、日本人が「歯を失ってしまう原因」のトップに挙げられる身近な病気です。
しかし、初期段階で歯周病を自覚することは大変難しく、多くの方は症状が進んでから受診されます。
少しでも歯周病が気になる方、しばらく歯医者に行っていない方は早めに歯科医院にて検査を受けることをおすすめします。
当院の歯周病治療の特徴について
専門性の高い「根本的な歯周病治療と
予防管理」
当院では、歯周病と口腔予防管理のエキスパートである「日本歯周病学会 認定歯科衛生士」の資格を持つスタッフを筆頭に研鑽を重ね、“根本的な原因からの歯周病の改善”に取り組み、症状の早期発見・早期治療・予防に努めています。
- 精密歯周病検査による症状と原因の把握
- 軽度から重度歯周病まで治療可能
- フラップ手術、骨移植、歯周組織再生療法などにも対応
- セルフケア指導、長期的な予防管理によるサポート
- インプラント周囲炎の予防メンテナンス など
患者さまの生涯にわたるお口と全身の健康を見据え、一人ひとりの症状の原因と生活背景に合わせた専門性の高い歯周病治療と予防プログラムを実践しています。
歯周病に関する相談・セカンドオピニオン対応歯科医院
当院では、歯周病に関するご相談や、セカンドオピニオン患者さまの受け入れも行なっております。
「他院で治療できないと言われた」という患者さまが当院に来られ、無事治療を終えられたケースも実際にございます。
自身の大切な歯を残し長く健康に保ちたい方、埼玉・与野で歯周病の専門治療や予防を受けられる歯科医を探している方も、どうぞまずはご遠慮なく埼玉県さいたま市・与野駅前の歯医者|歯科医院【与野さとむら歯科】へご相談ください。
歯周病とは?
原因や全身の健康との
関連性について

歯周病(歯槽膿漏)とは?
歯周病(歯槽膿漏)は大きく分けて、歯肉炎と歯周炎にわけられます。歯肉に炎症がおきた状態を歯肉炎、歯槽骨などを支えている組織全体が崩れてしまう病気を歯周炎といいます。
日本人の場合、歯肉炎は10~20代前半で60%の人がかかっており、50才代で約80%のほとんどの人がかかっていると言われています。歯周病の恐ろしいところは、歯自体には何ら問題がないように見えても、歯周病の症状が進んでしまうと歯が自然に脱落してしまう点です。
また、痛みや腫れなどの自覚症状も出にくいことから「Silent Disease(=静かなる病気)」とも呼ばれており、気づかないうちに症状が進んでしまっているケースも少なくありません。
歯周病の原因とは?
プラーク(歯垢)
最も直接的な原因はプラーク(歯垢)です。
プラークは、虫歯菌や歯周病菌をはじめとするさまざまな微生物のかたまりで、プラーク1㎎のなかに約1億個の微生物がいるといわれています。歯と歯肉の境目に磨き残しがあるとプラークが溜まり、そこから歯周炎の前段階の症状が起こります。
歯石
歯石は通常の歯ブラシではとることができず、この歯石の上にどんどんプラークがたまります。
歯科医院での専門的な歯のクリーニングで、定期的に歯石を取り除く必要があります。
ストレスや生活習慣など
ストレス、妊娠、更年期、食生活、噛み合わせなど様々な要因が歯周病に関連していることが分かってきています。
タバコ(喫煙)
タバコを吸っている人は血流が悪くなり、歯周病が進みやすくなることが分かっています。
さらに炎症が起きてしまうと治りづらく、プラークも付着しやすくなり、歯肉の色も黒ずんできてしまいます。
糖尿病
身体の抵抗力が低下するため、歯周病も急速に悪化させることが報告されています。
歯周病と全身の健康との関連性
近年の研究では、歯周病の原因菌はお口の中だけでなく、全身の様々な健康に影響を及ぼすことが分かってきています。
特に、糖尿病や動脈硬化の症状がある方や、妊産婦の方、ご高齢者は歯周病菌によるリスクを可能なかぎり回避できるよう注意することが必要だと考えています。
糖尿病と歯周病
生活習慣病の代表ともされる糖尿病と歯周病ですが、この2つの病気にも深い関連があることが分かってきています。
抵抗性が大きく関与しており、歯周病治療を行うことで血糖値が改善に向かったという報告もあります。
動脈硬化と歯周病
歯周病菌が歯ぐきから血管の中へと侵入すると、心臓の周りにある血管の壁にはり付き、動脈が硬く狭くなるとされています。
結果として血液の流れは悪化し、心筋梗塞や狭心症などを引き起こすリスクが高まる可能性があります。
妊産婦さんと歯周病
歯周病菌による歯ぐきの炎症によって、サイトカインという物質が生じることがあります。このサイトカインが、低体重出産の原因となる早産や胎児の成長不足などに影響を及ぼす可能性があると言われています。
妊産婦の方や妊娠を望まれる方は、なるべく早めに歯科医院で検診を受けることをおすすめしております。
認知症と歯周病
歯周病は、歯を失う原因として最も多い病気です。
また、厚生労働省の統計では、アルツハイマー患者のほとんどが歯が無くなっているという報告もあり、口の中の環境と脳の働きとの関連性が分かってきています。
歯周病の根本改善には
「患者さまのご協力」が不可欠です
歯周病は日々の生活習慣との関連も深いことから、まず患者さまご自身に歯周病について正しく理解していただくことが、根本的な改善を図るために重要なポイントとなります。そうして、毎日の食生活やセルフケアなどの生活習慣を振り返り、“歯の寿命を縮めてしまう悪い習慣を改善していこう”とする強い意識が必要です。
当院では、症状に合わせた専門的な治療とあわせて、歯周病リスクを高める生活習慣を一緒に見直していくなど、一人ひとりの患者さまに寄り添いながら一緒に考える診療を重視して行なっています。
そして治療をして終わりではなく、治療後も定期検診や予防メンテナンスを通じて、二人三脚で健康なお口の環境づくりをサポートしてまいります。
歯周病治療の
精密検査について

なぜ歯周病に精密検査が必要?
一般的な歯周病治療では、あくまで簡易的な検査と、表面的な汚れを取っている程度に留まるため、その患者様がどういった経緯で歯周病が起こったのか、ご本人も歯医者も良く分からないまま終わってしまうのが実態です。
このようなことを防ぐために、当院では患者さまの症状や必要に応じて「精密歯周病検査」を行なっております。
精密歯周病検査の目的・内容について
精密歯周病検査は、歯周病の進行度を正確に把握し、適切な治療計画を立てるために行う重要な検査です。
この検査は、通常の口腔内検査に加えて、より詳細な情報を得るための追加的な手順を含みます。
精密歯周病検査によって、歯周病の初期段階や進行具合、さらには治療の必要性を正確に判断できます。
歯周病の
症状段階・治療の流れ

歯肉炎(歯周ポケットの深さ1〜2mm)
歯茎のみに炎症を引き起こしている状態です。痛みといった自覚症状はほとんどありませんが、歯磨きの時や硬いものを食べた時に出血しやすくなる場合があります。
- 治療方法
歯科衛生士によるスケーリングやSRP(スケーリング・ルートプレーニング)で丁寧に歯石を除去し、毎日の正しいセルフケアについて指導させていただきます。定期的に通院し、良好な状態が保てるようにメインテナンスをしていきましょう。
軽度歯周炎(歯周ポケットの深さ3〜4mm)
歯を支えている骨(歯槽骨)が溶け出した状態です。歯磨きの時に出血したり、歯がうずく、歯茎が腫れぼったく感じるなどの症状があらわれます。しかし一般的な初期段階では、まだ無症状なことが多く注意が必要です。
- 治療方法
歯科衛生士がプロの技術で歯石や歯の着色汚れを除去し、毎日のセルフケアを正しく行えるように指導させていただきます。良い状態を維持するためのメインテナンスも定期的に受けましょう。
中等度歯周炎(歯周ポケットの深さ5~7mm)
歯を支えている歯槽骨が1/3~2/3ほど溶けた状態です。水がしみるようになったり、歯磨きをすると歯茎から血が出たり、歯茎が腫れたり治ったりの症状を繰り返します。また、歯がぐらぐらと動揺しはじめ、膿が出たり口臭が強くなる場合もあります。
- 治療方法
ここまで歯周病が進行してしまうと、歯磨きなどのセルフケアだけでは改善が望めません。歯科衛生士が歯肉の中にたまった歯石を取り除きます。また状態によっては麻酔が必要になる場合があります。
重度歯周炎(歯周ポケットの深さ7mm以上)
歯を支えている歯槽骨が2/3以上溶けた状態です。歯の周りを指で押すと白い膿がにじみ出て、口臭が強くなる場合もあります。歯磨きの際には頻繁に出血するようになり、歯が動揺して硬いものが噛みにくくなることがあります。放置してしまうと、歯が自然と抜け落ちるケースもあります。
- 治療方法
歯周病が重度にまで進んだ場合は、外科手術が必要になるケースがほとんどです。手術によって、歯の周りのプラークや歯石等の汚れを徹底的に取り除きます。また、歯周病に罹った歯の周辺の骨や歯肉を再生させる『歯周組織再生療法』を行うことで、残っている歯をより長く残すことができる可能性があります。
歯周病で抜歯が必要?
歯を抜く・抜かない治療のメリット
歯周病では、抜歯を行った方が良いケースや反対に歯を抜かずに治療する方が望ましいケースなど、さまざまです。
当院では、あらかじめ抜歯する/しない場合のメリットやデメリットなどを丁寧にご説明した上で、患者さんの状態やご希望に合わせて治療を行います。
歯周病で抜歯を行った方が良いケースや、歯を抜かずに治療するメリット・デメリットなどについては下記のページでまとめて解説しています。
歯周病治療の種類・特徴について

当院では、軽度から重度歯周病治療まで幅広く対応可能です。
患者様の症状やご希望に合わせて、最適な歯周病治療と予防方法をご提案いたします。
スケーリング
ケーリングとは、歯科医院で行う歯周病治療の基本的な方法の一つで、歯の表面や歯周ポケット内に付着した歯垢(プラーク)や歯石を除去する治療法です。歯周病の原因となる細菌が歯垢や歯石に潜んでいるため、それらを物理的に取り除くことで歯茎の健康を改善し、歯周病の進行を防ぎます。
歯周組織再生療法
歯周組織再生療法は、歯周病によって失われた歯周組織(歯を支える歯槽骨や歯根膜、セメント質など)を再生させることを目的とした治療法です。従来の歯周病治療では、進行した組織の破壊を食い止めることが主な目的でしたが、この療法では失われた組織を再構築することで、歯を長く健康に保つことが期待されます。
フラップ手術
フラップ手術は、進行した歯周病に対して行われる外科的治療法で、主に歯周ポケットの改善や歯槽骨の再生を目指します。この手術は、歯茎を切開して歯周病の原因となる歯石や感染を取り除く方法であり、歯の保存や歯茎の形態改善に有効です。
骨移植
歯の骨移植を伴うフラップ手術は、歯周病の進行により歯槽骨(歯を支える骨)が大きく損傷した場合に行われる治療です。歯槽骨が損失すると、歯の支えが不十分になり、歯がぐらつくことや最終的には抜歯のリスクが高まります。フラップ手術と骨移植を組み合わせることで、歯を保存し、骨の再生を促進することを目指します。
歯周組織誘導法(GTR)
歯周組織誘導法 (Guided Tissue Regeneration, GTR) は、歯周病によって破壊された歯周組織(歯槽骨、歯根膜、セメント質)を再生させるために行われる歯科治療法です。この方法では、歯周病の治療後に特殊な膜(バリアメンブレン)を使用し、組織の再生を促進します。
インプラントの歯周病
(インプラント周囲炎)について

インプラント周囲炎と歯周病の違い
インプラント周囲炎(しゅういえん)とは、「インプラントの歯周病」とも呼ばれる感染症のことです。
インプラント周囲炎は、通常の歯周病と同様に、お口の中の細菌が原因となります。
インプラントの治療後においても口の中を清潔に保つ必要がありますが、ご自身の歯磨きが不十分であったり、定期的に歯科医による専門のメンテナンスを受けなかった場合、インプラントと歯肉の境目から細菌が侵入してインプラント周囲からの出血や炎症が起こるリスクが高まります。
放置してしまうと、やがてインプラントが脱落してしまう結果となるのです。
また、インプラント周囲炎は、天然歯の歯周病と比べて自覚症状が現れにくいだけでなく、症状の進行速度も非常に早い傾向にあるため注意が必要です。
インプラント周囲炎を予防し、
インプラントの寿命を保つには?
「一生モノ」とも言われるインプラントも、長期間にわたって快適に使用していくには、「毎日のセルフケア」とあわせて、「定期的に歯科医院で検診やメンテナンスを受ける」ことが最も基本的かつ有効な方法となります。
治療後の適切な予防管理を行えば、インプラントの10年後の残存率は90%以上とされており、生涯にわたり安定して使い続けることが期待できます。
歯周病治療の費用・
保険治療と自費治療の
違いについて

基本的な歯周病の治療や予防処置は保険適用内で受けることができます。
ただ、歯の保険治療には使用できる材料や治療法などに制限があるため、より精度が高く長持ちしやすい治療や予防を求める場合は、自由診療を検討するのも一つです。治療前に歯科医師としっかり相談しましょう。
当院では、保険・自費両面における幅広い治療の選択肢をご用意しております。歯科衛生士と力を合わせ、患者さまの未来の健康と笑顔につなぐお手伝いをいたします。